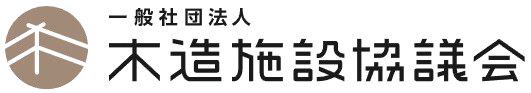暮らしのお役立ち情報
リノベで読み解く、鉄骨造と古民家の共通点
先日、鉄骨造の建物を、大空間を活かしてリノベーションする面白さをご紹介しました。
(『鉄骨リノベーションで暮らしが広がる』参照)
実は、鉄骨造の建物には、日本の伝統的な古民家と非常に似通った部分があります。今回は、鉄骨造と古民家構造の"骨太な構造"という共通点に焦点を当て、ふたつのリノベーションの可能性について考えてみたいと思います。
鉄骨造と古民家構造の共通点

一見すると正反対に思える鉄骨造と古民家ですが、構造的な視点で見ると意外な共通点があります。重量鉄骨のH型鋼による頑丈な骨組みと、古民家の太い柱や梁。これらの構造はどちらも"大空間を支える構造体"として、現代の一般的な住宅では実現が難しい広々とした空間を可能にしてくれます。
たとえば、古民家特有の『田の字』の間取りでは、中央の太い柱を中心として周囲に部屋が配置されています。柱と梁で建物を支えており、耐力壁という“構造上必要な壁”がないため、広々とした空間が実現できます。
重量鉄骨造も、頑丈な鉄骨柱と鉄骨梁で建物を支えているため、内部は完全フリー。
これらの構造的特徴が、リノベーションにおいて大きな可能性を生み出します。
自由な間取りを叶える骨組み

こういった構造上の特徴により、鉄骨造の建物は店舗やオフィスといった大空間を必要とする建物に多く用いられます。古民家は、襖を開け放つことで座敷や茶の間がひと続きになるため、冠婚葬祭や法事といった人が多く集まる場面でも田の字の間取りが活用されてきました。
こうした自由度の高さが、鉄骨リノベーションや古民家再生において本領を発揮します。
壁や建具を取り払ったワンルームのような広がりのあるLDKや、来客をもてなす広々とした玄関ホール、視界をさえぎるものがない吹き抜け空間など、現代住宅のリノベーションでは難しいダイナミックな住空間を生み出すことができます。
鉄骨リノベーションと古民家再生
昭和後期の高度経済成長期に建てられた、鉄骨造のビルや工場、倉庫。これらの建物を現代の暮らしに合う形へと再構築することで、まちの風景は少しずつ変わっていきます。
一方で、100年以上もの長きに渡り住み継がれてきた古民家の再生も、根強い関心を集めています。地域の記憶を宿した趣ある佇まいは、福井の自然や文化に寄り添う住まいづくりと親和性が高く、それらの建物を再生して住まうことで、土地の魅力を再発見することにもつながるのではないでしょうか。

時代も素材も異なるふたつの建物が、今の暮らしにしなやかに呼応していく。永家舎ではこれからも、そんなリノベーションを手がけてまいります。
関連記事:古いものを愛でる、日本人の心
関連記事:古民家の息吹を現代につなぐ永家舎のリノベーション
関連記事:木造だけじゃない、住まいの構造