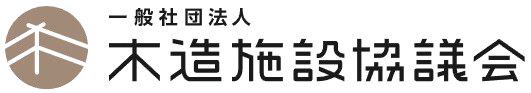暮らしのお役立ち情報
リノベーションで住み継ぐ福井の家
【令和6年住宅・土地統計調査】(総務省統計局)によると、福井県の持ち家率は約73.4%。長期的にはやや減少傾向にあるものの、全国的には依然として高い水準にあります。さらに、住宅1戸あたりの平均床面積も、福井県は全国平均を大きく上回っています。
高まるリノベーションの重要性
戸建ての持ち家、大きな家、広い庭。福井の人たちは、そんなゆとりある環境で育ってきました。
その背景には、“家を住み継ぐ”という福井の文化があります。

一方で、福井県においても新築住宅の着工戸数は年々減少傾向にあります。
少子高齢化による人口減少に加え、建築資材や人件費の高騰など、さまざま要因が考えられますが、こうした時代だからこそ、既存の住宅ストックを活用するリノベーションの重要性が高まっています。
環境への負荷を抑える観点からも、国は新築に偏らず、既存住宅を適切にメンテナンスしながら長く住み継ぐ住まい方を推進しています。
リノベで使える福井の補助金
福井県でも各市町村と連携し、リノベーションを支援するさまざまな補助制度を整備しています。
たとえば、ここでも何度かご紹介している『県産材を活用したふくいの住まい支援事業』では、県産材を使ってリフォームすることで補助金が交付されます。
このほかにも『住み続ける福井支援事業』として、空き家の取得とリフォーム、多世帯同居のためのリフォーム、子育て世帯や移住者に対する支援など、ライフスタイルの変化に応じた多様な制度が用意されています。
また、伝統的な福井の民家を対象とした『福井の伝統的民家活用推進事業』では外装や構造、外構の改修に対して補助を行うほか、『木造住宅の耐震化に関する補助制度』では耐震診断と耐震改修に対して、『住まい環境整備支援事業』では住まいのバリアフリー化を目的として、安心・安全で快適な暮らしを支える制度が整っています。
受け継がれる福井の未来
先祖から受け継いだ住まいには、長年にわたって土地の気候や風土に寄り添い、培われてきた知恵が詰まっています。こうした伝統の知恵を活かしながら、現代の暮らしに合わせて住まいをリノベーションする。それによって、福井の住文化はこれからも豊かに、そしてしなやかに進化していきます。

持ち家というかけがえのない資産を活かし、次の世代へと住まいを受け継いでいく。それは、ただ単なる家の継承ではなく、福井という地域の未来そのものを時代へと手渡していくことにもつながるのではないでしょうか。
関連記事:どうする?残された祖父母の家
関連記事:永家舎なら最大315万円のリノベ補助金
関連記事:今、県産材を使う会社が増えている?