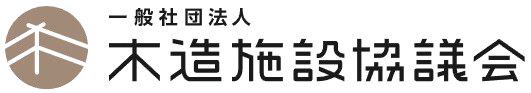暮らしのお役立ち情報
リノベーションでワークスペース革命!【事例付き】
2025/11/25
目次
変化する働き方に応える住まいづくり

テレワークの普及により、住まいに求められる役割が大きく変化しました。以前は「仕事は会社、家は休息の場」という明確な区分けがありましたが、今はその境界線が曖昧になりつつあります。
新しい住まいの価値観
家は休息の場から『生活と仕事を両立する拠点』へと進化を遂げています。朝起きて通勤する代わりに、リビングの一角やかつて物置だった部屋がオフィスに。この変化は決して一時的なものではなく、これからの住まいづくりにおいて避けて通れないテーマになっています。特に重要なのが、家族がいても集中できる環境づくりの必要性。子どもが遊ぶ声、テレビの音、キッチンでの家事の音。これらの生活音と仕事を両立させるには、空間の使い方に工夫が求められます。
オフィスのような機能的な空間でありながら、長時間過ごしても疲れない、むしろ創造性を刺激するような心地よさ。この相反する要素を融合させることが、理想的なワークスペースづくりの鍵となります。
ワークスペースが必要になる背景
在宅勤務が始まった当初は、ダイニングテーブルやリビングのソファで何とか凌いでいた方も多いでしょう。しかし、長期化するにつれて、専用スペースの必要性が浮き彫りになってきました。腰痛や肩こりといった身体的な負担。家族の動きが気になって集中できない精神的なストレス。仕事と生活の境界が曖昧になることで生じる、オンオフの切り替えの難しさ。こうした課題を解決するには、やはり"仕事のための場所"が必要です。
また、オンライン会議が日常化したことで、背景に映り込む生活感への配慮も求められるようになりました。洗濯物やおもちゃが散らばった部屋では、プロフェッショナルな印象を保つのが難しい。バーチャル背景を使う手もありますが、やはり実際の空間が整っている方が、信頼感は増すものです。
福井の暮らしとワークスペース
福井は持ち家率が高く、比較的ゆとりのある住空間を確保しやすい地域。都市部のマンションと比べると、ワークスペースを作る選択肢も広がります。使っていない和室がある、子どもが独立して空き部屋ができた、二階の一部屋が物置になっている。こうした"もったいないスペース"を見直すことで、本格的なワークスペースを確保できるかもしれません。
また、福井の気候を活かした空間づくりも魅力のひとつ。夏は涼しく、冬は雪景色を眺めながら仕事ができる。窓の配置を工夫することで、四季の移ろいを感じながら働ける環境を手に入れることができます。
ワークスペースの3つのスタイルと選び方

効果的なワークスペースには3つの基本パターンがあります。それぞれに適した職種や働き方があり、どれを選ぶかで快適さが大きく変わってきます。
ウェブ会議が多いなら個室に近い環境、パソコン一台で完結する仕事なら場所を選ばない。もう一つ重要なのは"どれくらい家族とつながった状態で仕事をしたいか"という視点です。子どもの様子を見守りながら作業したいのか、完全に仕事に没頭したいのか。その答えが、最適なスタイルを導き出してくれます。
関連記事» 快適なリモートワークのためのワークスペース計画
| タイプ | 集中度 | 開放感 | コスト | 適した職種 |
|---|---|---|---|---|
| 完全個室 | ★★★ | ★ | 高 | 会議多め・機密情報扱い |
| 半個室 | ★★ | ★★ | 中 | 子育て中・柔軟な働き方 |
| オープン | ★ | ★★★ | 低 | 短時間作業・家事の合間 |
それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
1.完全個室タイプ - 集中力重視
リモート会議が多い職種に最適なスタイル、「小さなオフィス」です。顧客との商談、社内ミーティング、プレゼンテーション。画面越しとはいえ、ビジネスの場面では背景や音環境への配慮が不可欠。完全個室なら、音漏れを気にせず通話できる環境が手に入ります。家族の生活音が会議に入り込む心配もなく、逆に仕事の会話が家族の邪魔になることもありません。
資料や書類の保管スペースを十分確保できるのも大きな利点。デスク周りをすっきりさせつつ、必要な書類にすぐアクセスできる収納計画が可能になります。
機密情報が多い場合のセキュリティ面での安心感も見逃せません。顧客情報や企業の内部資料を扱う仕事では、家族といえども見られたくない情報があるもの。施錠できる個室があれば、そうした懸念も解消されます。
2.半個室タイプ - 家族との距離感
パーテーションや本棚で緩やかに区切り、視線は遮りつつも家族の気配は感じられる。そんな絶妙なバランスを実現するのが半個室タイプです。子どもの様子を見守りながら作業可能な環境は、小さなお子さんがいる家庭に特に人気。完全に隔離されているわけではないので、何かあればすぐに対応できますし、コミュニケーションも活発に。
開放感を残しつつプライベート空間を創出できるのも魅力のひとつ。壁で完全に仕切ってしまうと圧迫感が出やすい住まいでも、半個室なら空間の広がりを保ちながら仕事に集中できるエリアを確保できます。
3.オープンタイプ - フレキシブル活用
リビングやダイニングの一角に設置するオープンタイプは、最も気軽に在宅ワークを始められるスタイル。家事や育児の合間に利用しやすく、ちょっとしたメールチェックや書類作成なら十分に対応できます。初期費用を抑えながら効果的な環境づくりができるのも大きなメリット。大がかりな工事は不要で、造作カウンターやデスクの設置だけでスタートできます。
家族とのコミュニケーションを保ちながら仕事ができるため、孤独感を感じにくいのも特徴。リビングの一角で作業していれば、家族が声をかけやすく、自然な会話も生まれやすくなります。
コストパフォーマンスを最大化する方法

限られた予算で最大の効果を生むには、既存の空間を上手に活かすことが重要です。増築するなどゼロから作り上げるのではなく、今ある構造や設備を見直すことで、驚くほどコストを抑えながら理想の環境を手に入れられます。
既存の間取りを活用する
既存の間取りや設備を活かしつつ、必要最小限の変更で理想空間を実現。これがリノベーションならではの強みです。例えば、和室を洋室へ転換し、押入れや床の間部分をワークスペースに変える。押入れは奥行きがあるため、デスクカウンターを設置すれば足元もゆったり。床の間は造作棚やファイル収納として活用すれば、無駄なスペースがありません。
デッドスペースとなりがちな廊下の一部や階段下も、空間を有効活用するうえで見逃せない選択肢。特に階段下は作業をするには十分な広さがあり、コンパクトなワークスペースにぴったり。採光の工夫次第で、隠れ家のような雰囲気も演出できます。
リノベーションでは、新築と違って既存の構造を活かせる分、コストを抑えやすいのが特徴。窓の位置や電気配線なども、使えるものは残しながら計画することで、予算の大部分を本当に必要なところに集約できます。
まずはオープンタイプで
あとから個室感が必要だと思えば、衝立やパーテーションを活用する方法もあります。あらかじめ壁を追加できるようにしておけば、将来的な変更も容易です。初期費用を抑えつつ、将来的な拡張性も確保できる。リノベーションの場合は"空間の有効利用"がテーマになるため、使える面積に限りのある新築に比べると、比較的個室化しやすいという利点もあります。既存の部屋の一部を区切るだけで済むケースが多く、構造的な制約も少ないため、後から個室にする場合でも工事が比較的簡単に進みます。
段階的にワークスペースを充実させていく。そんな柔軟な発想が、長く使い続けられる空間づくりにつながります。
永家舎のワークスペース・リノベーション事例
実際の施工事例から見る、空間活用法をご紹介します。それぞれの暮らし方、働き方に寄り添った空間は、これからワークスペースを考える方にとって、きっとヒントになるはずです。隠れ家みたいなワークスペース【鯖江市】
50代男性の「これからの暮らしを愉しみたい」という想いを形にした事例。築50年の住宅を"紳士な隠れ家"へとリノベーションしました。
ポイント:
・LDK横に書斎スペースを設置
・コーヒーと音楽が似合う大人カフェ風デザイン
・趣味時間と生活空間の絶妙なバランス
リビングとのつながりを保ちながらも、扉を閉めれば自分だけの時間を過ごせる設計。仕事だけでなく、読書や音楽鑑賞など、趣味の時間も心ゆくまで楽しめる空間になっています。落ち着いたトーンの内装と、こだわりの照明が、長時間過ごしても疲れない心地よさを生み出しています。
実例» 紳士な隠れ家
寝室隣接型プライベート書斎【坂井市】
2世帯住宅のフルリノベーションで、寝室に隣接した書斎を設置。夜寝る前の一時を趣味の読書で愉しむプライベートな空間を実現しました。
ポイント:
・寝室と書斎の連続性を活かした設計
・読書に最適な落ち着いた空間デザイン
・プライバシーを重視した配置
寝室とワークスペースを隣接させることで、就寝前のリラックスタイムと仕事や趣味の時間をスムーズに切り替えられる動線を確保。2世帯住宅という特性を活かし、家族との適度な距離感を保ちながら、自分だけの時間を大切にできる配置になっています。
読書灯の配置や本棚の高さ、椅子に座ったときの視線の抜け方まで、細部にこだわった設計が、長く愛される空間を作り上げました。
実例» リノベーションで快適さと、心豊かな暮らしを実現。
縁側を活用した明るい書斎【大野市】
平屋スタイルのリノベーションで、元々の縁側を光の入る明るい書斎に生まれ変わらせた事例。無駄なスペースをなくしながら機能的な空間を確保しました。
ポイント:
・既存の縁側スペースの有効活用
・自然光を最大限取り込む設計
・平屋暮らしに適した動線計画
・コスト効率の良いスペース活用術
縁側という、現代の暮らしでは使いにくくなりがちなスペースを、明るく開放的なワークスペースへ。大きな窓から差し込む自然光が、一日中心地よい明るさを保ちます。
平屋ならではのワンフロアで完結する動線を活かし、家事の合間にも立ち寄りやすい配置に。庭を眺めながら仕事ができる贅沢な環境は、リノベーションだからこそ実現できた空間活用の好例です。
実例» 平屋スタイルで退職後の人生を豊かに
成功するワークスペースリノベーションのポイント

永家舎の施工実績から導き出された、失敗しないワークスペースづくりの法則があります。計画段階でしっかり押さえておきたいポイントをまとめました。
関連記事» しっくり、ほっこり。造作家具のある暮らし〜ワークスペース〜
使用目的の明確化が最重要
まず考えるべきは、そのワークスペースで何をするのか、という基本中の基本。作業内容と使用時間の把握から始めます。一日のうち何時間そこで過ごすのか。午前中だけなのか、夜遅くまで使うのか。時間帯によって必要な照明も変わってきます。
リモート会議の頻度と重要性も大きな判断材料。週に何度も会議があるなら、背景に映り込むものや音環境への配慮は必須。逆に会議がほとんどないなら、もっと開放的なスタイルも選択肢に入ります。
必要な設備・機器のリストアップも忘れずに。パソコン、プリンター、モニター、書類。何をどれだけ収納するかで、必要なスペースの広さが見えてきます。
家族構成と生活パターンの分析も重要です。小さな子どもがいる家庭と、夫婦二人の暮らしでは、求められる環境がまったく違います。家族の一日の動きを想像しながら、最適な配置を考えていきます。
照明・空調・音響への配慮
自然光と人工照明のバランスは、快適性を大きく左右する要素。窓からの自然光は心地よい明るさをもたらしますが、パソコン画面への映り込みには注意が必要です。一日の光の変化を考慮した窓配置を。朝の柔らかな光、午後の強い日差し、夕暮れ時の陰り。それぞれの時間帯で快適に作業できるよう、カーテンやブラインドの選択も含めて検討します。
設置場所ごとの温熱環境を考慮することも大切。特に個室タイプの場合、エアコンの風が届きにくかったり、冬場に冷え込んだりすることも。快適な温度を保つための工夫が求められます。
生活音と作業音の適切な遮音設計も忘れてはいけません。キーボードを叩く音、椅子を引く音。意外と響くこれらの音が、家族の邪魔にならないよう配慮することで、お互いにストレスのない環境が生まれます。
家族での共有を考えた設計
子どものスタディスペースとして使ったり、ワークスペースにしたり、家族のライフステージに合わせて柔軟に活用できる設計。これからのワークスペースには、こうした可変性が求められています。今は仕事場として使っていても、将来的には趣味の部屋に、あるいは子どもの勉強部屋に。用途が変わっても使いやすい空間にしておくことで、長く愛される場所になります。
造作家具も、あまり用途を限定しすぎない方が後々便利。デスクとしてだけでなく、作業台としても、ディスプレイ棚としても使えるような汎用性のあるデザインを選ぶと、暮らしの変化に柔軟に対応できます。
まとめ

働き方の変化は、住まいの在り方も大きく変えました。形に囚われず、今後の働き方に合わせて自由に計画する。それがリノベーションでワークスペースを作る最大の魅力です。
完全個室にするのか、家族との距離感を保つ半個室にするのか、それともオープンなスタイルにするのか。正解はひとつではありません。大切なのは、自分の働き方、家族との時間、そして予算のバランスを見極めること。
既存の空間を活かせるリノベーションなら、新築では難しいコストパフォーマンスも実現できます。押入れを書斎に、縁側を明るいワークスペースに。今あるものを見直すことで、新しい可能性が見えてくるはずです。
関連記事 » ワークスペースとスタディスペースの違い
今月の人気記事